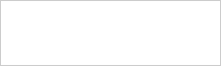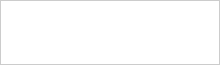子どもたちは各種の体験を得ることで好奇心が刺激され、勉強に積極的になります。8月7日に各省庁で開催された「こども霞が関見学デー」のイベントに参加した≪もんじゅ≫の女子中学生Nさんに、当日の様子を書いてもらいました。
**************************************
先月8月7日に私はデジタル庁で開催された中学生対象ワークショップ「生成AIを使って考える未来の日本」に参加しました。デジタル庁の職員さんが講師としてアロハシャツ姿で登場されました。最初にデジタル庁とはどのような組織なのかについての説明から始まり、AIを使ってスクリーンタイムを管理しているお知り合いのお話など、AI利用の実例を紹介してくださいました。
この日参加した中学生は全国から応募した約20名で、3つのグループに分かれて生成AIの未来について討論をしました。生成AIを勉強に活かす方法と、生成AIが発展していくにつれて求められる人間の能力はどのように変化するのかについて考えようという議題が与えられました。私たちのグループは将来なりたい職業を想定して、AIとのかかわり方で職業ごとの共通点と相違点を話しあいました。
グループ内の2人のメンバーは将来希望する職業をすぐにあげてくれましたが、その他の4人は特に思い浮かびませんでした。そこで、そもそも仕事には何があるかを生成AI を使って調べることから始めました。意外にもAIは「職業を決める前には健康を維持することが大事です」との回答を提示し、みんな笑ってしまいました。こちらのAIへの質問のしかたがうまくなかったのかもしれませんが、AIも珍回答をするものです。
それぞれのグループで出た意見やAI体験を、各グループの代表が報告しました。私も報告を担当しました。私たちのグループ内のメンバーの意見で共通していたのは、まずAIに関する基本的な知識をもつべきこと、さらに様々な情報を受け入れる柔軟な思考方法が必要であること、そしてAIが進化したとしてもやはり自分自身の好奇心と行動力が特に重要だということでした。求められる職業の専門的な知識に相違はあっても、AIを利用する方法に大きな差はないということも私は報告しました。
デジタル庁の方によれば、生成AIは特定の質問の言葉の後に来やすい解答を選ぶという確率で選ぶ「連想ゲーム」のようになっているそうです。取り込む情報源によって生成AIの解答が異なってしまうという性質があるため、どの生成AIを使うべきかを見極める力が必要だと、教えてくださいました。生成AIの可能性と課題を知ることができ、私たちが将来AIとどのようにかかわるべきかについて考える良い機会になりました。
- 投稿タグ
- 霞が関